今回紹介する本は、斎藤孝先生の「悔いのない人生」、副題は死に方から生き方を学ぶ「死生学」です。
前回の投稿で、マンダラチャートを紹介しましたが、私の現在のマンダラチャートの中心に書いてある目的が「死ぬ特に後悔しない」ですので、まさに今の私にぴったりの本ではあります。
このブログを読まれている方の年齢はさまざまでしょうが、人生も後半に入ってくると、意識するしないに関わらず「死」に向き合わざるを得なくなります。自分がどのような死に方をするか、誰もわかりませんが、できれば大きな後悔なく死んでゆきたいものです。
TVで売れっ子の斎藤先生が、古今東西の書物から先人たちの考え方を紹介してくれています。この本を道しるべに、原作を読んでみるのもいいのではないかと思います。貝原益軒の「養生訓」、V・E・フランクルの「夜と霧」、西郷隆盛の「西郷南洲遺訓」などの中から、私が特に印象に残った「葉隠」の一説を紹介しておきますね。
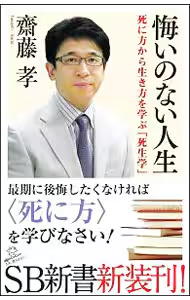
●「葉隠」
「葉隠」と言えば、「武士道とは死ぬことと見つけたり」という言葉が非常に有名です。この書は、江戸時代中期に肥前の国佐賀鍋島藩の藩士だった山本常朝の話を田代陣基が筆録したものだそうです。
「端的只今の一念より外はこれなく候。一念一念と重ねて一生也。ここに覚え付き候えば外に忙しき事もなく、求むえる事もなし。ここの一念を守って暮らすなり。皆人、ここを取失ひ、別に有る様にばかり存じて探促いたし、ここを見附け候人なきもの也。守り詰めて抜けぬ様になることは、功を積まねばなるまじく候。されども、一度たづり附き候へば、常住になくとも、最早別のものにてはなし。この一念に極り候ことを、よくよく合点候へば、事少なくなる事あり。この一念に忠節備わり候也と。
(訳)まさに現在の一瞬に徹する以外にはない。一瞬、一瞬と積み重ねて一生となるのだ。ここに考えがおよべば、ほかにあれこれとうろたえることもなければ、探し回ることもない。この一瞬を大切にして暮らすまでのことだ。一般に人は、ここのところを間違って、別の人生があるように思い、それを尋ね回って、この点に気づく者がいない。この一瞬をいつも大切にして怠らないようになるには、年功を積まなければならないものである。しかしながら、一度その境地にたどり着けば、いつもそのように思い詰めていなくとも、その境地を離れることはない。この一瞬に全てがあるということを十分に心得たならば、物事は簡単に運ぶものだ。この一瞬に忠節がしなわっているのである。
最近では「人生100年時代」が流行り言葉で、やれリスキリングだ、やれ転職だと騒がれていますが、今の立場で最大限の努力をしている人は、どのくらいいるのでしょうか。新しい環境を求めて移ったとしても、結局、不満な点を理由にまた新しい環境を求める、その繰り返しで人生を終えてしまっては、なんとも勿体ないですね。
かと言って、ただ漫然と今の環境に甘んじていてもいけないと思います。将来なりたい自分の姿を思い描きながら、1日1日を大切に生きるということになるのでしょうか。
皆様が悔いのない人生を送られることを祈念いたします。
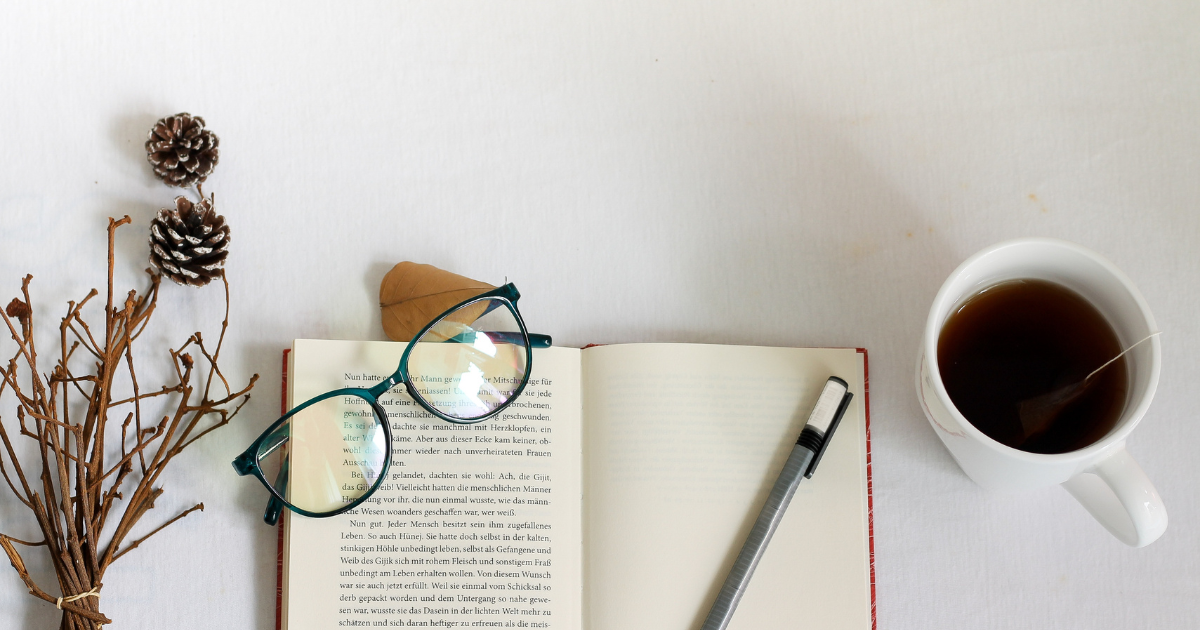
コメント